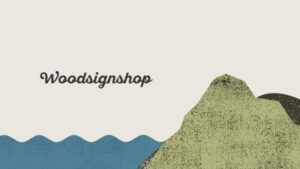長男K
長男K『木材』は地球に還元されるサスティナブルな循環物質として認識されているけど、
はるか昔は木材の一部、
【リグニン】といわれる物質は分解されにくく
そしてどんどん蓄積されていく時代があったんだって。
それが様々な要因で石炭になっていったんだって・・・
その後、リグニンも分解される菌が登場して・・・
って、大学の授業で学んでね~面白いなぁと思ったんだよね~

ほんとだね!
それは面白い★
少し調べて覚書として残しておこう!!
シルル紀後期(約4億43百万年前〜約4億19百万年前)、地球は新しい時代を迎えました。
【リグニン】を合成する進化した植物が舞い降り、陸上で威張って直立し、木々の姿勢を変えました。
リグニンを含む植物は驚くほど頑丈で、当時は腐朽しにくく、地表には分解されにくい植物の残骸が広がっていきました。
これらの植物は驚くほど頑丈で、当時は腐朽しにくく、地表には分解されにくい植物の残骸が広がっていきました。
その後、湿地や沼地に堆積した植物の一部が、長い時間を経て石炭へと姿を変えていくドラマが始まります。
 リグニンから石炭へ
リグニンから石炭へリグニンから石炭が形成された過程は非常に長期間にわたるもので、その具体的な時期は難しく特定することができません。
しかし、一般的には古生代の石炭紀(約3億59百万年前〜約2億99百万年前)にかけての時代において、石炭の形成が主に起こったと考えられています。
二畳紀前期にかけて、植物が多様化し、湿地に堆積した遺骸は分解されにくいまま地中へ。高温・高圧の条件のもとで、石炭が大量に生まれました。
しかし、物語には変化が訪れます。古生代末〜二畳紀ごろ、【白色腐朽菌】と呼ばれる微生物が登場しました。この菌はリグニンを本格的に分解できる能力を持っており、私たちが普段目にするキノコもその代表的な存在です。
キノコをはじめとする菌のおかげで、木は完全に分解され、栄養が土壌へと循環する新しいサイクルが生まれました。石炭形成の減少にはこの菌の進化が大きく関わっていたと考えられています。もちろん、気候変動や海水準の変化、大陸配置などの影響もあったとされています。
三畳紀前半には乾燥化が進み、“石炭形成の空白”が生じた地域もありました。こうして、かつては地球に蓄積されるだけだった木が、菌の登場によって再び循環の一部となったのです。
※白色腐朽菌(多くはキノコの仲間)はリグニンを分解する能力を獲得した時期と石炭形成の減少の時期が一致するとの研究があり、これが一因と考えられています。ただし、気候変動や海水準の変化など他の要因も大きく影響しており、単一原因で説明できるわけではありません。※

私たちは木に魅力を感じ、木製看板の製作に携わっています。
木の魅力の一つに『地球に還元される物質』ということもありました。
かつては木も地球にとって【蓄積されるだけの存在だった】という事実は驚きでした。
今でいうと、もしかするとプラスチック問題的なものだったのかもしれないですね。
プラスチックも元は石油。プラスチック問題もこの先このような変遷を遂げることもあるのか…
プラスチックも石油由来の物質であり、自然界で分解されにくい存在です。
いつか未来に、プラスチックを分解する新しい仕組みが登場し、リグニンのように循環の一部となる日が来るのかもしれません。
などといろいろなことに想いを、考えを馳せてみました。
私たちは地球の歴史、木の歴史、未来へと続く物語の一部に生存していてこの現代の恵みに感謝して日々精進していくことが大切なのかな・・・
と自らも顧みる良いきっかけとなりました。
最後までお読みくださり、お付き合いくださりありがとうございました。